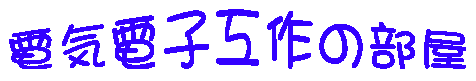
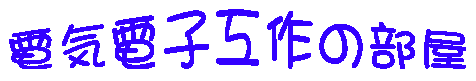
最近の更新内容を掲載しているページです。 ホームページ開設以来の変更来歴は来歴の小部屋を参照して下さい。
Edition 6.494 (2026-02-08)
部品・ユニットの小部屋に「RF Demo Kit」 を新規追加。
今シーズンやっと八代を訪問する機会に恵まれました。 今回は越冬ナベヅル16羽のうち13羽を確認できた「八代のナベヅル堪能」となりました。 八代到着時は雲海に没しており10m先もまともに見えない状態で今回はナベヅル観察は無理と思われました。 その後、幸いにも霧が徐々に薄れてくるとねぐら方面から鳴き声が聞こえてきました。 昨シーズンまでは最大でも3羽の飛来 の経験しかありませんでしたが、今回は何と7羽のナベヅルの飛来を観察できました。 しかも、いつもはすぐに給餌場に降りるのですが、今回は霧のためかしばらく給餌場付近を周回して降りました。 さらに霧のためか飛来がいつもより遅く、空が明るくなってからの飛来となりナベヅルをはっきりと確認できました。 雲海さまさまでした。 その後、野鶴監視所から計8羽の越冬ナベヅルを観察できたのも初めてでした。 2グループに別れていましたが、給餌場エリア で仲良く餌をついばんでいました。
野鶴監視所からの帰り道、八代盆地を歩いていると見慣れた鳥の姿と鳴き声がしてきました。 当初はデゴイかと思っていましたが、デジカメのズームで遠方を観察するとデゴイとともにナベヅルが5羽いるではありませんか。 今まで何度も通った道ではありますが、現認できたのは初めてです。 これで合わせ13羽を観察できました。 とても充実した「八代のナベヅル堪能」となりました。
Edition 6.493 (2026-02-01)
所蔵品の保管がますます問題となってきました。 HPコンテンツ関連の図書やキット類の保管品だけではなく、「山口県参考資料」やデーターブック、電子部品・電気部品カタログ類、ストック用電子部品など様々な図書・品物があります。 毎年、処分しなければと思いつつ、とうとう破綻寸前となりました。 にも関わらず、部品切れ補充を発端に、またもや小さ目段ボール分の部品・キット類を購入してしまいました。 ショッピングは楽しいのですが、その後の保管が大変となります。 懲りていません。 これはたまらないと、まずは図書類の整理のために図書を書棚から段ボール箱に移すことにしました。 でも、丁度よい大きさのダンボ―ル箱が手持ちでは有りませんでした。 ネットで調べると適切な大きさ・厚みの段ボール箱を見つけました。 数日後、それでなくても空きスペースがないにもかかわらず、購入した保管用段ボール置場を確保しなければならなくなりました。 一体、何してるの!!!!!
Edition 6.492 (2026-01-25)
今更ながらRTCチップを初めて触ってみました。 月毎の日数変化やうるう年対応を考えると専用のRTCチップは楽でした。 これまで、ソフトウエアで時刻・時間を得る際にはマシンサイクルとステップ数との格闘、GNSS利用は小型化・スタンドアローン化を考えるとちょっと腰が引けていました。 RP−2040はにRTC機能はありますがあまり評判はよろしくないようですし、とても期待していたRP−2350ではRTCが無くなるなどちょっと残念な事ばかりでした。 やはり外付けRTCしかないとの思いで「今更ながら」となりました。 しかし、RTC−4543は製造中止品であることに気付きませんでした。 だめだこりゃ!
Edition 6.491 (2026-01-18)
部品・ユニットの小部屋に「GPS受信機 シリアル出力タイプ L1+L5デュアルバンド対応 デッドレコニング機能 1PPS出力付 (GT-505GGBL5-DR-N)」 を新規追加。
部品・ユニットの小部屋の「DTMFレシーバモジュール (M8870A) / MT8870 DTMF音声デコードモジュール (HW-05)」 を更新。
「GPS受信機 シリアル出力タイプ L1+L5デュアルバンド対応 デッドレコニング機能 1PPS出力付 (GT-505GGBL5-DR-N)」 を購入して11ヶ月後でやっと動作確認ができました。 時間がかかりました。 デッドレコニング機能にとても期待を持っていましたが、残念ながらデッドレコニング機能を正常に機能させることができませんでした。 移動手段の問題もありますが、信号の無い直線500mの道路が近くにはほとんど有りません。 この地は平野部が少ないのです。 初めて大阪や関東を訪れて、360°見回しても山の見えない景色に驚嘆した記憶があります。
「DTMFレシーバモジュール (M8870A) / MT8870 DTMF音声デコードモジュール (HW-05)」 はボタン操作表記を間違っていました。 大阪府のF様よりご連絡を頂くことで間違いを修正できました。 この場を借りて御礼申し上げます。
Edition 6.490 (2026-01-11)
電子工作マガジンの定期刊行終了に伴い、参考資料の小部屋の更新のタイミングを失ってしまいました。 今後は気になっていた図書について随時紹介していくつもりです。 現在は参考図書として電気電子工作関連の図書を多く収集していますが、それ以外にも集積回路・半導体ディスクリート部品関連の大量のデーターブック/データーシートがあります。 これらを集めるきっかけは、業務で電子回路に関わっていると思われていない環境で、数少ない電気電子技術屋さんだった事もあり、電子回路部品関係の業者との接触が無く、情報は自ら取得・収集するしかなかったためです。 当時、趣味の世界では汎用トランジスタ2SC372・2SC945から2SC1815に移行する次期でもありましたが、これらのデーターシートすらなく、CQ出版社が出版していたトランジスタ規格表やトランジスタ互換表が頼りでした。 とある(当方にとっての)事件があり、データシートの読込み・理解の大切さ、記載情報は自己責任で理解しなければならないこと(掲載情報を素直に読み取ってはダメ)などとても痛い思い・経験をして、デバイス情報の収集癖がますます強くなりました。 しかし、集めた資料をどうしましょう。 集めたデバイスのデータシート類はネット上で公開されていないものも多くあり、なかなか廃棄する勇気が出ません。
Edition 6.489 (2026-01-04)
長年生活していると「捨てられない!」ネタがどんどん溜まってきています。 今回はマウスでしたが、それ以外に家電品・オーディオ機器など沢山待ち構えています。 でも、キットやパーツの未使用ストック品(HPネタ未作成品)も沢山残っています。 さて、今年はどんなネタを消化できるでしょうか。
ところで、「捨てられない!」ネタが増えたので、Memorandumの小部屋の項目として「捨てられない!」を独立してもいいかなと思い始めています。 「捨てられない!」ネタを新規追加時は考えてみようかと思っています。
Edition 6.488 (2025-12-28)
「EVOLTA NEOを買われてしまいました。 単1乾電池持ち時間を調べようの巻」の取りかかりは、これからもっと暑くなるだろうという時期でした。 今は大掃除をしなければという時期です。 とても時間がかかりました。 疲れました。 お金もかかりました。 ごみ集積所での乾電池の廃棄も半年に1度です。 できれば電池測定はやりたくありません。
Edition 6.487 (2025-12-21)
「PT−1005B Test Leads (PT-1005B)」 を使い始めて10ヶ月以上となります。 当初は先端が針状で危なくキャップの装着が必要、使用する度にキャップの脱着が必要、キャップ紛失に気を使うなど使勝手が悪い印象を持っていました。 が、使い続けているうちに狭ピッチのリード線の測定が容易、小面積パターンの測定が容易、表面酸化膜を除去(破壊)して導通を得やすいなどの長所が勝って、今では「PT−1005B Test Leads (PT-1005B)」 を使うのが当たり前となっています。 また、使っているうちに先端が劣化するのではとの懸念がありましたが、10ヵ月経過してもたいした劣化は見受けられませんでした。 これらの背景より、単なるテストリードではありますが部品・ユニットの小部屋に追加することにしました。 一言、今のところお勧めです。
Edition 6.486 (2025-12-14)
FMワイヤレスマイクはこの世界に踏み入る一つになっています。 古くは「図解 ワイヤレス・マイク製作集」の製作記事を参照して製作にいそしみ、「FM−ステレオ・トランスミッタ」でステレオ送信が身近になり、「NS73M使用FMステレオ・トランスミッター・キット (K-02498)」のデジタル化で(お遊びの)FMステレオ送信ではアナログの世界は終わったと思うに至りました。 そして今回の「FM stereo transmitter kit module board」 でほぼ完成形に至ったと思いました。 よく出来ています。 あと、モノラル放送もできればと思うところです。
Edition 6.485 (2025-12-07)
キットの小部屋に「ホイールローダー (J-7 1793)」を新規追加。
ダイソーで物色していると電子工作の文字か目に留まりました。 その商品が「電子工作 ホイールローダー (J-7 1793)」でした。 見るからにモータ付きのギヤボックスと電池により動作する組み立て式おもちゃでした、 これは当方の分類では「電子工作」ではなく「 電気工作」です。 そうなんです。「電子」と「電気」の違いにこだわりを持っているのです。 ただ、その境界・相違点となると曖昧なままです。 ざっくりと、電子部品と呼ばれる部品を使うと「電子工作」、リレー・電磁接触器などの機械的構造部品を使うと「電気工作」と識別しています。 とはいえ、変圧器だけを使うとどうなの?かつてのリレ−式電子計算機は電気工作なの?と判断に悩むところです。 いずれにしても、本ホームページタイトル「電気電子工作の部屋」は、このようなこだわりから名付けています。
Edition 6.484 (2025-11-30)
部品・ユニットの小部屋に「MAX6675 Module + K Type Thermocouple Thermocouple Senso Temperature Degrees Module (HW-550)」 を新規追加。
「MAX6675 Module + K Type Thermocouple Thermocouple Senso Temperature Degrees Module (HW-550)」の価格は1,000円未満と安価でした。 しかし、純正のMAX6675に関して、Digikeyでは製造中止の+無し品(MAX6675ISA)が1,051円ちょい、精算中止品となっていない(アクティブ)+有り品(MAX6675ISA+など)は1,912円〜2,759円となっています。 価格面から判断するに、到底純正のMAX6675とは思えません。 しかし、AliexpressやAmazon.co.jpではK型熱電対センサ付きで単価1,000円未満の商品が多く見受けられます。 確かに安いのは嬉しいことですが、とても気になる状況です。 ただ、純正のMAX6675が何故こんなに高価な理由が分かりません。
Edition 6.483 (2025-11-23)
部品・ユニットの小部屋に「パルスバッテリスポット溶接機 S788H」 を新規追加。
実は「パルスバッテリスポット溶接機 S788H」を入手したのは約5年前です。 いつかは立ち上げなければと思いつつ優先順位が下がってしまいました。 そのため、現在は日本向け商品として外観などが変更されているようです。 当然ですが価格もアップしています。 また、本Webページ公開時点において在庫切れで再入荷未定のため入手できるか不明です。 バッテリ用に限定すればもっと小型のスポット溶接機もあるようですが、「パルスバッテリスポット溶接機 S788H」はそれなりの出力電流を流すことがでるので素人作業でも確実な溶接ができるかなと思いました。
Edition 6.482 (2025-11-16)
「G−PORTER GP−102」を利用して頻繁に軌跡ロギングをしています。 時たまロギングに失敗する場合があるため、可能な限り2個同時にロギングをするようにしています。 これまでも一方のログデータが適切ではなく(乱れ・ログ不可)ても、もう一方のログデータはそれなりに取得しており、適切な軌跡取得ができていました。 しかし、11月13日の13時過ぎに数分間の差はありましたが、2個ともほぼ同時間帯にログできなくなっていました。 そういえば太陽フレアンのニュースがあり、宇宙天気予報・太陽フレアを確認すると11月11日の夜頃に活発な活動があったようでした。 この影響なのかな? いずれにせよ「G−PORTER GP−102」を酷使しているため、リチウム電池や液晶に劣化が目立ってきました。 「G−PORTER GP−102」は中古もほとんど出まわっておらず、あっても数万円という途方もない価格となっています。 また、現在市販されている類似製品も見当たりません。 類似製品でもいいから入手したいと持っていますが、難しいようです。
Edition 6.481 (2025-11-09)
最近の「4−Band Digital FM MW SW Radio (DD5024-4-Band)」もそうですが、最近のラジオはとてもシンプルな構成で製作できることを実感させてくれます。 ラジオといえば高周波機器で育った身にしては、IFTの無いラジオは想像すらしていませんでした。 今更ながら「Memorandumの小部屋」の「第2のゲルマニウムラジオ!! ソフトウェア・ラジオの製作。」の驚きを思い出します。
Edition 6.480 (2025-11-02)
乾電池類の廃棄にはとても困っています。 マンガン乾電池はゴミ収集対象ですが、それ以外の電池は廃棄する手段がありません。 今回のリチウム2次電池の他に、CR2などのリチウム1次電池、ニッカド電池、ニッケル水素電池、コイン電池、水銀電池尾など、自治体回収対象外の電池がたまっています。 皆さんはどうされているのでしょうか。
Edition 6.479 (2025-10-26)
「Memorandumの小部屋」の「USBケーブル、なんじゃこりゃ! USBケーブルチェッカの製作」でUSBケーブルチェッカ―を製作しましたが、ちょっと懲りすぎでした。 目的を断線チェックに限定すれば今回の「DT3 Data Cable Detection Board Type−C Micro USB C Cable Tester」 がシンプルで使いやすく好ましいです。 シンプルなだけではなく、基板搭載USBコネクタのコスト以下の低価格低でした。 他人事ではありますが。利益確保できているのかな?
Edition 6.478 (2025-10-19)
「Multifunctional data Cable (L19)」で初めてLightningコネクタなるものを扱いました。 このコネクタを製品に利用している某A社はピィー(XXXXXXXX)と認識しており1980年代から一切の関わりを避けています。 当方は 世間一般的な某A社評価を全く理解できない人です。 とはいえ、今回は某A社以外の製品の機能確認をするため、泣く泣くこのコネクタ(某A社以外製造品)を利用 する環境を整えたものです。
Edition 6.477 (2025-10-12)
キットの小部屋に「易しいラジオきっと (K-7642Q1CS)」を新規追加。
「易しいラジオきっと (K-7642Q1CS)」のイヤフォンの使い方(接続方法)を知りませんでした。 イヤフォンのコモンラインはGNDレベル(コモンレベル)に接続するものの思い込んでいました。 今回のような使い方(イヤフォンにDC成分を含んだ音声信号を加える)が適切かどうかは別にして、確かにイヤフォンを電源スイッチとして兼用することができます。 ただ、 音量調整や左右音声バランス調整ができないなど不便な点ばかり目に付きます。
Edition 6.476 (2025-10-05)
Memorandumの小部屋に「DDSで「とにかく変調」(その1)」を新規追加。
アマチュア無線コールサイン取得後、すでに半世紀を過ぎました。 この間、無線関係の電気電子工作はあまりやっていません。 実は今回の変調機能についても、変調を目的に試行したのは初めての経験でした。 図書関係でいろいろ読んではいましたが、図書に記載されているような変調波形を確認したことも今回初めてだと思います。 実際にやってみると図書どうりにならない事が多々ありました。 まだまだ学ぶ事は沢山あります。 さて、(その2)はいつになることやら。
Edition 6.475 (2025-09-28)
参考資料の小部屋に「電子工作マガジン No.6 8 2025年秋 AUTUM」を新規追加。
参考資料の小部屋に今後公開予定の資料を追記。
「電子工作マガジン No.68 2025年秋 AUTUM」に定期刊行終了の記事が掲載されていました。 薄々感じてはいましたが、とうとう来たかという感じです。 アマチュア無線、電気電子工作など当方にとって身近にあった趣味は時代に合わなくなってきて、当方自体を含めて衰退期に入っています。 とても寂しい思いですが、これも時代ですね。 早く断捨離などを始めろを言われているようにも思えました。 が、やってはダメだと思いながらもAliexpress商品や参考図書など、ペースは減っているものの依然と増え続けています。 最近、抵抗の在庫切れが判明してちょっと焦っています。 久しぶりとなりますが秋月電子通商の通販を利用しようかな。。。。。
Edition 6.474 (2025-09-21)
キットの小部屋に「電池BOX入りFMラジオキット (K-7088B)」を新規追加。
先日から気温も下がり、セミの声はわずかとなり、稲穂の上をトンボが飛び交いさらに秋を感じるようになりました。 しかし、お彼岸近くになっても彼岸花の赤色や白色の花、いや、つぼみすら見かけません。 まだ季節は秋ではないですよと言っています。 まあ、頬かむりしなくても歩けるようになっただけでも助かります。 何せ安物タオルの頬かむりは見栄えが良くないですからね、
しばらく前から何故かラジオ関係にハマってしまいました。 今回の「電池BOX入りFMラジオキット (K-7088B)」はその余波です。 全ての始まりは購入済のGNSSモジュールから始まって、それを始める前にはあれをやっておかなければ、これをやっておかなければとプロジェクトの玉突き状態となりラジオにたどり着きました。 風が吹けば桶屋が儲かる状態です。 一体いつになればGNSSモジュールに戻れるのでしょうか。 でも、今となってはその過程の記憶が残っていません・・・・・
Edition 6.473 (2025-09-14)
柿が色づき始めるなど、やっと秋らしさを感じる機会が増えてきました。 とはいえ、日中はまだまだ30℃超えの日があるようです。
今回の電力伝送の動作確認でどのようなデータを採取しようかと迷ってしまいました。 このデータが欲しい、あのデータも欲しいと考えていると膨大なデータ採取となる、また、再現性の確保が難しいなどに気付きました。 結局、デバイスメーカのデータを利用を参照すれば済みそうなので、波形観測を主としたデータ採取となりました。
Edition 6.472 (2025-09-07)
今回初めてチップキャパシタのDCバイアス特性を測定しました。 強誘電体のため数値が常に変化しています。 グラフにプロットするとガタガタになると思いながら測定しましたが、実際にグラフ化すると思った以上に滑らかなプロットができたようです。 また、測定結果からグラフ化用のデータを得るため、久々にEXCELで複素数関数を利用しました。 EXCELの複素数関数を利用することに気付かなければ、きっとグラフ化を諦めていたでしょう。
Edition 6.471 (2025-08-31)
キットの小部屋に「Electronic Scale 1KG Weighing Soldering Practice Kit (TJ-56-630)」を新規追加。
「プログラム書き込みサービス」および「パーツ有償サービス」を中止。
「USBシリアル変換ケーブル スケルトン (M-00720)」「USBシリアル変換ケーブル クレー色 (M-02746)」「FT232 USBシリアル変換ケーブル VE488 (M-08343)」のデータ番号誤記(1548〜1550→1648〜1650)を訂正。
ロードセルによる重量計測の再現性は決して悪くないと思っていましたが、今回のキット「Electronic Scale 1KG Weighing Soldering Practice Kit (TJ-56-630)」の動作確認の結果は意外でした。 現象自体の確認が十分ではないためどこに要因があるのか全く不明です。 少なくとも使い勝手を含めて現状のプログラムでは使い物にはならない印象です。 いつか機会があれば要因調査をしてみたいのですが。。。。。 時間が欲しいです。
Edition 6.470 (2025-08-24)
キットの小部屋に「DIY Kit LM317 Adjustable Regulated Voltage 110V to 1.25V−12.5V Step−down Power Supply Module PCB Board Electronic kits」を新規追加。
今回のキット「DIY Kit LM317 Adjustable Regulated Voltage 110V to 1.25V−12.5V Step−down Power Supply Module PCB Board Electronic kits」は珍しく組立説明書が付属している、梱包に緩衝材が使われていたなどの理由で、AliExPress 扱いの商品としては比較的良い印象があります。 でもこれらの事は日本の会社のブランドで販売している一般的なキット類では当たり前の事です。 しかし、この当たり前と思っていた事は、実は「やりすぎ」「過剰品質」だったのかもと思うようにもなりつつあります。 「Made in Japanの商品は素晴らしい」などの論評を目にすることがありますが、当方のような「Japan as No.1」を体験した世代が過去の栄華にすがりついているのではと思えて仕方ありません。 最近よく利用しているAliExPress 扱いの商品品質が当たり前のレベルと思る強この頃です。
Edition 6.469 (2025-08-17)
部品・ユニットの小部屋に「OCXO 10MHz Frequency Standard Reference Module Crystal Oscillator Constant Temperature Board Module」 を新規追加。
周波数カウンタは何種類か入手・製作していますが今回の 「OCXO 10MHz Frequency Standard Reference Module Crystal Oscillator Constant Temperature Board Module」 の周波数を精度よく測定することができません。 以前より精度の高い周波数カウンタが欲しいと思っていましたが間に合いませんでした。 GNSSモジュールの1PPS出力を用いた高精度の10MHzを得ることができる(1〜2万円以下で小型の)機器が販売されていますが、当方には高精度の周波数を得ることのできる(内部デバイスのバラつき・不安定さ、熱の影響などを考慮した設計・部品選定をしているのは不安でたまらなく、入手していません。 GNSSから出力されるている信号が高精度の周波数であることは(何となく)理解することはできますが、その精度を何故GNSSモジュールで維持てきるのが、周辺回路にその精度を維持する能力があるのか、全く理解できていないというのが正直なところです。 1ppbの怖さ、凄さを身に染みています。
Edition 6.468 (2025-08-10)
キットの小部屋に「DIY Kit Digital Watch Electronic Clock Single−chip LED Digital Electronic Watches Clock Module LED With Cover For arduino NEW」を新規追加。
今回もまたもやボタン電池の大幅定格オーバーの利用例でした。 ボタン電池の大きさ(薄さ)は魅力的ですが、取り出すことのできる電流はわずかであることの認識がとても薄いようです。 電圧ばかりに気を取られているのか、それともボタン電池の大きさの魅力に負けて意図してボタン電池を利用しているのか・・・・。 後者でなければ良いのですが。 ボタン電池で利用できる消費電力の部品を剪定する努力をして欲しいですね。
Edition 6.467 (2025-08-03)
電池ボックスは子供の頃からお世話になっています。 単1乾電池はモータや豆電球を負荷として利用していましたが、接続すれば動作するという漠然としたイメージしかありませんでした。 今回も何気なしに単1乾電池用電池ボックスを入手して利用しようとしていました。 当然、本Webページのコンテンツ対象になんか思ってもいませんでした。
電池ボックス利用時に電流・電圧を測定していたところ期待したような結果となりません。 ここから深みにはいりました。 とりあえず電池ボックスを本Webページのコンテンツ化をしましたが、本来の用途で電池ボックスが使えないと判断しており予定が大きく狂ってしまいました。 電池ボックスを用いない対策を検討している最中です。 今更ながら車のバッテリ配線を大きなボルトでカシメている理由を認識できました。
Edition 6.466 (2025-07-27)
1608(ミリ表記)より小さいサイズのチップ部品を利用していましたが、チップ部品利用時、ピンセットを持つ手につい力が入ってしてしまいチップ部品があちこちに飛散することが多々ありました。、飛散した部品が小さすぎて探す気も失せます。 そのため3216サイズのチップ部品をあらたに集める機会が増えました。 今回もその一環です。 いや、数列91に魅せられて思わず衝動買いした商品です。 衝動買いのオンパレードです。
ところで、今回の抵抗値測定に際しても、チップ部品の飛散が止まることもありませんでした。 チップサイズは部品飛散の主要因ではなかったようです・・・・・
Edition 6.465 (2025-07-20)
SMAコネクタ付きの同軸ケーブルを使い始めたのは「GigaSt Ver4」ではないかと記憶しています。 その後、「USB−SA44B USB−TG44A USB−SA44−ABA」を利用し始めると、周波数領域の測定ではBNCコネクタ同軸ケーブルからSMAコネクタ同軸ケーブルに移り変わってきました。 小型であるSMAコネクタは取り扱い易くて、BNCコネクタを利用する機会はオシロスコープ以外ではほとんど無くなりました。 ただ、この頃は同軸ケーブル長が数m物を利用していました。 対象の周波数も数MHz〜100MHzと、今思えば比較的低い周波数を用いた測定に利用していました。 次の節目は「NanoVNA−H」を入手してからでした。 GHz帯域を手軽に取り扱えるようになると同軸ケーブルの長さの影響が目に付くようになることが増えてきました。 さらにGHz帯域を対象としていない同軸ケーブルだと測定再現性の懸念も出てきました。 などと、いろい問題もかかえながらGHz帯を測定していました。 長さの短いSMAコネクタ同軸ケーブルが欲しいと思っていたところで、今回の安価な「5PCS SMA Male to SMA Male Plug Jack RF Connector Extension Cable 10cm」を入手するに至りました。 今回も衝動買いの言い訳でした。
Edition 6.464 (2025-07-13)
部品・ユニットの小部屋に「SMA Male to SMA Female cable assembly 15cm with 7 units sma adapters sma male sma female rpsma male (SMA4)」 を新規追加。
今回の「SMA Male to SMA Female cable assembly 15cm with 7 units sma adapters sma male sma female rpsma male (SMA4)」 も必要に迫られて購入したものではなく、またもや「これは安い!!!!!」で購入したものです。 目視・触った感じではブランド品とは一線を画した品質の印象です。 でも、いざというときには役立ってくれるはずです。 でもいつ使うのかな? ちなみに、2ポート対応できるように2セット購入しています。 こうして更にストック品が増えていくのでした。
Edition 6.463 (2025-07-06)
暑い熱い日々が続きます。 持ち歩いている「G−PORTER GP−102+」も熱を持ってしまいます。 例年のよりひと月早い感じです。 それにしても暑い熱い。
今回、10個もの50Ωダミーロードを入手しましたが全部使いきることはないと思っています。 今回は「これは安い!!!!!」、どの程度の品質の商品なのか調べて(測定して)みたいと思ったが間違いの始まりでした。 完璧に無駄な買物です。 このようにして不要部品(無駄部品)が増えていくのでした。
Edition 6.462 (2025-06-29)
部品・ユニットの小部屋に「100MHz−3GHz RF Balun Transformer RF Single ended Differential Signal Converter Balun 1:1」 を新規追加。
ホームページの先頭説明を見直し、および、「English homepage is here.」のリンクを削除。
AliExpressで購入する機会が増えています。 電子機器・部品関連を主に購入しているのではなく、実は園芸用資材を購入するついでに電子機器・部品を購入しています。 かつてはダイソーで安く購入できていたものが廃番となり、とても高価な商品しか入手できなくなりますた。 そこで少しでも安く購入できないかと AliExpressを利用するようになりました。
今回の「100MHz−3GHz RF Balun Transformer RF Single ended Differential Signal Converter Balun 1:1」 も別の園芸用資材を購入してカートを決済する直前に何かないかと探して見つけたものです。 「AD620 Microvolt mV Voltage Amplifier Signal Instrumentation Module Board」 で味をしめて、よく吟味せずに商品タイトルの「ADF4350」「ADF4351」に釣られてポチッしました。 商品タイトルの付け方が上手ですね。 じっくり時間をかけて商品選択をしないといけません。
Edition 6.461 (2025-06-22)
参考資料の小部屋に「電子工作マガジン No.67 2025年夏 SUMMER」を新規追加。
参考資料の小部屋に今後公開予定の資料を追記。
少なくとも15年は経過しているはずの扇風機が勝手に電源オフする不具合症状が出ており、この症状が悪化してほぼ使えない状態となりました。 一昨年にこの不具合症状に気付き、電気 ポットなど他の電気製品の電源オンのタイミングで発生していました。 当初は扇風機のオンスイッチを何度か押すことで電源オンを保持できていましたが、今では必ず電源オン 後、すぐに電源オフするようになりました。 徐々に悪化したことより電解キャパシタの劣化と思って制御基板を確認しましたが、電解キャパシタは1個(470μF 16V)のみで、 ケースの膨らみも無く、静電容量の低下・ESRの明らかな増加も生じていませんでした。 とりあえず新品の電解キャパシタに交換しましたが、不具合症状は改善しませんでした。 制御基板を目視確認しましたが、外観上の異常やはんだ付け異常は見当たりませんでした。 修理成功すれば「Memorandumの小部屋」の「捨てられない*****」のコンテンツとして取り上げようと算段していましたが、叶いませんでした。 仕方なく今回は10数年振りに新品扇風機を購入しましたが、不具合の扇風機は・・・・・ やっぱり捨てられません。 いつか原因を探してみよう・・・・・ 電気製品のゴミ屋敷になるのではと心配しています。
Edition 6.460 (2025-06-15)
「AD620 Microvolt mV Voltage Amplifier Signal Instrumentation Module Board」 にはAD620と記載のあるデバイスが搭載されていました。 「AD620がこの値段で買える!」と思わずボチッしちゃいました。 現品を入手して外観を観察するとあれれ? とても疑っています。 動作確認をしましたが、まあ思ったような信号増幅はしてくれていますので「まあいいか」とは思っています。 アナログデバイス社製の純正AD620と比較してみたい衝動に駆られていますが。。。。。 こらこら、まだやらなければいけないことが山積みです。 おっと、今頃になってもトマト苗の植替えが待っています?????。 GNSSモジュールの立上げもやらなければ・・・・・
Edition 6.459 (2025-06-08)
I2Cはとても便利です。 今回の「MCP4725 EEPROM搭載12ビットD/Aコンバーターモジュール (108677)」はDC電源の出力電圧設定に用いることができないかと思って入手したものです。 DC電源特性測定時に制御の特性調査においてような低速動作にはうってつけです。 間違ってもDDSに使おうと思ってはいけません。 今回の出力波形測定でも、プログラム起因の波形ジッタが気になりました。
タケノコとも闘いも終焉を迎えつつあります。 まだわずかですが生えてきています。 最終成果は立木に隠れて巧妙に育っている竹と言ってもいい背の高いタケノコを残さずに見つけて根絶できるかにかかっています。
Edition 6.458 (2025-06-01)
部品・ユニットの小部屋に「ENS160+AHT21 CARBON Dioxide CO2 eCO2 TVOC Air Quality And Temperature And Humidity Sensor」 を新規追加。
「ENS160+AHT21 CARBON Dioxide CO2 eCO2 TVOC Air Quality And Temperature And Humidity Sensor」に搭載されているENS160とAHT21の測定データはどこまで信用していいのか疑問です。 通電後、しばらく放置しておく必要があるのかもしれませんが、通電後数分後に得た温度データは高めで、このまま利用したいとは思えませんでした。 正確と思われる温度計が手元にあれば比較できるのですが、残念ながら信じられる温度計が手元にはありません。 ましてや相対湿度やENS160の測定値はどこまで信じてよいのやら。 とりあえず今回はそれらしい変化をする数値を得ることができたので、これで動作確認終了としました。
Edition 6.457 (2025-05-25)
部品・ユニットの小部屋に「Raspberry Pi Pico 2 (129604)」 を新規追加。
「Raspberry Pi Pico 2 (129604)」の動作確認のために開発ツールとしてArduino IDEを利用しています。 かつてはアセンブラ専門でC言語(相当)は使っていませんでしたが、Arduino IDEと出会ってからはC言語風の「Arduino言語」にハマっています。 Aruduino IDEを利用することでマイクロプロセッサーが異なっても同じソースを利用することができています。 今回も同じソースプログラムを再コンパイルするだけで済みました。 Arduino IDEには感謝です。
Edition 6.456 (2025-05-18)
「125Pcs 25Types Micro Tact Push Button Switch Assorted Kit」は1種類ごとに小袋に入っていました。 合計で25袋ありますが、実は最初に数えると24袋しかないと勘違いしていました。 かつては目視で数えることは容易にできていましたが、最近は目視での計数が難しくなってきました。 今回は小袋を指でつまんで数えました。 結果的には、それでもまともに数えることができていませんでした。 その後、画像撮影する際にちゃんと25袋あることが確認できました。 それはそれで一安心でしたが、とうとう指でも数えることができなくなったのかとショックです。 野菜などの小さな種をピンセットを使って数える(多くは24個や30個)ときも、±1個の数え間違いが増えてきました。 若い頃には想像すらできないことですが、受け入れるしかありません。
Edition 6.455a (2025-05-12)
部品・ユニットの小部屋の「Dual Mode Signal Generator PWM Pulse Frequency Duty Cycle appropriate Module (XY-LPWM3)」 を更新。
Edition 6.455 (2025-05-11)
部品・ユニットの小部屋に「Dual Mode Signal Generator PWM Pulse Frequency Duty Cycle appropriate Module (XY-LPWM3)」 を新規追加。
「Dual Mode Signal Generator PWM Pulse Frequency Duty Cycle appropriate Module (XY-LPWM3)」は前回公開した「1Hz−150kHz Signal Generator Module Adjustable PWM Pulse」とを同じシリーズのようです。 今回「Dual Mode Signal Generator PWM Pulse Frequency Duty Cycle appropriate Module (XY-LPWM3)」のWebページを作成するうえで初めて気付きました。 回路的には 「Dual Mode Signal Generator PWM Pulse Frequency Duty Cycle appropriate Module (XY-LPWM3)」の方が改善されているようですが、やはりプルアップ抵抗付きのオープンドレイン出力や周波数同一のDUTY独立可変3出力の目的が理解できません。
Edition 6.454 (2025-05-04)
「1Hz−150kHz Signal Generator Module Adjustable PWM Pulse」は動作確認をするにつれて疑問が次々と出てきました。 結局最後まで回路設計者の意図を理解できず、に動作確認を途中で止めることにしました。疑問が出てくるのはちょっと困りものですが、勉強にはなります。
Edition 6.453 (2025-04-26)
「0805 SMD inductor Assorted KIT (0805-1NH-22UH)」のWebページは比較的短時間で作成できると思っていました。 しかし、つい「LiteVNA64」を用いてインダクタンスを測ってみようと思ったのが間違いの始まりでした。 当初は既存DUTを利用していましたが測定結果の 解釈に困ることも多く有り、とうとう専用DUTを製作して全て再測定してしまいました。 凝るのもいい加減にしないといけませんね。 時間がかかって仕方ありません。
Edition 6.452 (2025-04-20)
部品・ユニットの小部屋に「PE4302 RF Attenuator Module」 を新規追加。
今回使用したデバイス「PE4302」はとても優秀な印象を持ちました。 メーカのPeregrine Semiconductor Corp.は今まで利用した記憶の無いメーカですが、高周波関係でとても興味の湧くデバイスを設計製造している会社でした。 ただ、残念なのが「PE4302」は既に製造中止品のため、メーカーサイト上で「PE4302」のデーターシートなど技術資料を見つけることができませんでした。 現行品には「PE4312」があり、電源範囲など使いやすくなっていました。
ニュースではタケノコの裏年とアナウンスしていますが、当方の近所では全くその気配は無く例年のようにニョキニョキと生えてきています。 ウォーキング途中でもタケノコの先端が顔を出しているのを多数見かけます。 撤去しないと道端が傷むだろうにと思いながら通っています。 当方もタケノコとの闘いは最盛期を迎えつつあります。 数日目を離すと、もう顔・頭を出しています。 見つけ損ねて大きく育っている輩も出てきています。
先週から水色の新幹線を見かけるようになりました。 初めて見た日はハローキティ新幹線の通過予定時間に見かけたので、ハローキティ新幹線が終了したのかと思ってしまいました。 調べると水色新幹線はワンピース新幹線でした。 ハローキティ新幹線とは異なり、運行時間・運行期間は日々変化するようです。 また、ハローキティ新幹線も継続して運行されるようです。 しばらくは2種類の新幹線を楽しむことができるようです。
Edition 6.451 (2025-04-13)
固定側USBコネクタはプリント基板にハンダ付けして利用される事が多いです。 しかし、パネル取付けをしたい場合にはプリント基板を介してパネル取付けするのは余分なスペースを要します。 せっかくのコンパクトなコネクタを生かすことができません。 「USB Type−Cコネクターパネル取付キット (K-17640)」もありますが、金具の高さが省スペースとなっていません。 何か良い製品がないかと思っていたところに「10 Pcs USB 3.1 Type C Sockets With Screw Mounting Plate (QC3C0567-4Pin)」を見かけて入手してみました。 パネル取付け面はプリント基板製でしたが、強度も有り思ったようなコンパクトさでした。 これならば利用してみようと気になりました。
いつものジョギング/ウォーキングコースに川沿いの桜並木があります。 ここに踏切があり、桜満開の頃には桜をバックにローカル線列車を撮影しようと撮り鉄さんたちがカメラをローカル線列車に向けて撮影しているのを見かけます。 この頃は撮影の邪魔にならないように気をつけないといけません。 今年も例年どおりに気をつけてウォーキングをしていると新幹線の音がするのでその方向に顔を向けました。 すると、満開の桜の枝の隙間から 青い空・春の日差しのもと、川面の花いかだと赤・ピンク色のハローキティ新幹線が通過していました。 ほんの数秒の出来事でしたが、何とも言えない素晴らしい景色となっていました。 以前の紫色系のエヴァンゲリアン新幹線では味わえない景色でした。 撮り鉄さんたちをみると、1〜2分後に通過予定のローカル線列車を撮影しようと踏切を向いて待ち構えていました。 桜とハローキティ新幹線は1日に1回のみ、しかも満開を迎えた直後の 晴天下の限定アングル には気付いていないようでした。
Edition 6.450 (2025-04-06)
今年もタケノコさんシーズンとなりました。 昨年同様、4月になってやっとタケノコさんとのお付き合いが始まりました。 また、なぜか昨年と同様に、この時期に「LiteVNA64」を触る機会が増えました。 毎年同じことの繰返しです。 でも、あと何年続けることかできるのかな? 体も含めて様々なモノが劣化してきています。 最近、何10年か振りにカードゲームの神経衰弱をしましたが、カードの種類・場所をまともに記憶できなくなっていました。 記憶だけではなく、熟考することも苦手になってきています。
熟考といえば、今回の「LiteVNA64」を用いた測定において十分な検討もせずに行き当たりばったりで何度も測定を繰り返してしまいました。 期待どおりの測定結果を得られなかったため、何度も測定方法・キャリブレーション方法を変えてに測定し直しました。 その結果、記録に残したデータはキャリブレーション直後の確認データと被測定物「Nanovna HT004 Signal Amplifier (HT004)」の測定値を合わせて75回となりました。 キャリブレーション用パーツのコネクタも劣化しつつあります。
Edition 6.449a (2025-04-01)
部品・ユニットの小部屋の「DC−4.0GHz Fixed Attenuator」 に掲載の特性測定グラフを修正。
「DC−4.0GHz Fixed Attenuator」 に掲載の特性測定グラフにおいて、S11の軸設定を誤って左側縦軸(Phase)に設定していました。 S11の軸設定を正しい右側縦軸(Magnitude)に設定し直した特性測定グラフに訂正しました。
End of This Page.