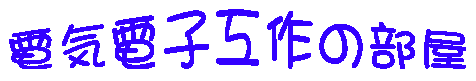
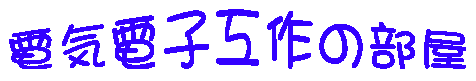
|
100MHz−3GHz RF Balun Transformer RF Single ended Differential Signal Converter Balun 1:1 |
末尾の注意事項をお読み下さい。
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
|
データ番号 |
1930 |
|||||||||||||||||
|
区 分 |
部品 |
|||||||||||||||||
|
分 類 |
高周波 |
|||||||||||||||||
|
品 名 |
100MHz−3GHz RF Balun Transformer RF Single ended Differential Signal Converter Balun 1:1 |
|||||||||||||||||
|
発売元 |
|
|||||||||||||||||
|
価 格 |
596円(送料・税込) |
|||||||||||||||||
|
主要部品 |
− |
|||||||||||||||||
|
電 源 |
− |
|||||||||||||||||
|
概略仕様 |
出典元:商品Webページ。 (タイプミスと推測される場合は、訂正しています。) |
|||||||||||||||||
|
付属基板 |
DykRadio RF Transformers |
|||||||||||||||||
|
付属ケース |
− |
|||||||||||||||||
|
外形寸法 |
基板単体 W 44.4mm D 18.1mm H 6.6mm (SMA−Rコネクタ含む) |
|||||||||||||||||
|
追加購入 部品 |
− |
|||||||||||||||||
|
コメント |
− |
|||||||||||||||||
|
改 造 |
− |
|||||||||||||||||
|
その他 (製作例) |
【 商品Webページ 】
輸送用封筒の中にプチプチにくるまれただけの基板が届きました。 【 パッケージ外観 】
【 基板外観1 】
【 基板外観2 】
【 基板外観3 】
【 基板外観4 】
【 基板外観5 】
【 基板外観6 】
【 基板外観7 】
トランス巻き線は端子用金属板に溶接取付けされていました。 【 基板外観8 】
【 基板外観9 】
【 基板外観10 】
動 作 例 平衡ライン用の測定器や50MHzを超えるオシロスコープを所有していません。 それでもと測定を試みました。 無理は承知で、被測定対象をバランではなく、逆位相出力できる電力2分配器と見なして「LiteVNA64」「デジタルオシロスコープ DS1054Z 50MHz 4ch 1GSa/s」を用いて特性らしき数値を得てみた結果を下記します。 本基板の入力ポートをRFAコネクタ、出力ポートをRFBコネクタ・RFCコネクタと見なしで「LiteVNA64」でS21のMagnitudeとPhaseを測定しました。 「LiteVNA64」は2ポートしかありませんので、測定は2回に分けて測定して、その結果を用いて電力分配比、RFBコネクタ出力とRFCコネクタの位相差を数値計算で求めました。 まず、 「LiteVNA64」PORT1をRFAコネクタ、PORT2をRFBコネクタに接続しました。 RFCコネクタには50Ωダミー抵抗で終端しました。 この状態でのS21測定結果を下記に掲載します。
【 動作確認時外観(全体) 】
【 動作確認時外観(本基板) 】
【 RFBコネクタ出力 S21 Magnitude 】
【 RFBコネクタ出力 S21 Phase 】
次に、「LiteVNA64」PORT1をRFAコネクタ、PORT2をRFCコネクタに接続しました。 RFBコネクタには50Ωダミー抵抗で終端しました。 この状態でのS21測定結果を下記に掲載します。
【 RFCコネクタ出力 S21 Magnitude 】
【 RFCコネクタ出力 S21 Phase 】
上記結果のMagnitudeを単純に加算してRFBコネクタ/RHCコネクタ出力のS21(順方向伝達関数)のMagnitudeとみなし、Phaseを引き算してRFBコネクタ/RHCコネクタ出力のS21(順方向伝達関数)のPhaseと見なしました。
【 RFBコネクタ/RHCコネクタ出力 S21 Magnitude相当 】
【 RFBコネクタ〜RHCコネクタ出力 位相差 】
上記結果より、電力伝達は50%〜約90%、位相差はほぼ180度(反転)の結果となり、ほぼ期待値どおりとなりました。 ここで止めるべきでした。 最後に出力波形を観測することにしました。 接続に際しては、基板上のRFBコネクタ〜RFCコネクタの中心導体間に50Ω(100Ω抵抗を2個並列)をハンダ付けしました。 「DS1054Z」の入力にSMA−R:BNC−P変換コネクタを取り付けて、RFBコネクタ/RFCコネクタ〜「DS1054Z」間はSMA同軸ケーブルで接続しました。 、観測する波形は「LiteVNA64」PORT1出力の100MHz連続波としました。 これは「DS1054Z」の帯域を越えていますが、絶対値は無視して、位相と振幅の大きさの比率を確認できればいいと割り切って利用しました。 なお、「LiteVNA64」PORT1出力は正弦波ではないと推測していますが、「DS1054Z」で波形を観測するとあたかも正弦波のように観測されます。 これは「Vector」表示機能によるもので、10MHzを超える波形観測は、「Dot」表示で実際のサンプリング値を表示して波形状態を確認しておく必要があります。 今回は、まあいいかというレベルでしたので、とりあえず「DS1054Z」の「Vector」表示による観測値を利用することにしました。 (実際には、正弦波出力できる「USBシグナル・ジェネレータキット(USB−DDS) 」の70MHz程度の波形を観測して、100MHzとそれほど相違のないことを確認しました。)
100Ωのチップ抵抗を2個重ねてハンダ付けしています。 【 波形観測時基板外観 】
【 観測波形 】
位相差についてはほぼ180度となりましたが、残念ながらRFB〜GND間電圧振幅(82.0mV)とRFC〜GND間電圧振幅(214mV)では倍半分以上の違いがありました。 最初の「LiteVNA64」測定結果とは大きく異なる観測波形となりました。 オシロスコープの観測の方が正しいと推測していますが、「LiteVNA64」の測定では正しく観測できない理由を理解できていません。。
|
データ作成者 CBA
注意事項
本表の記載内容はデータ作成者の現状を表しているものであり、キット本来の機能・性能を表しているものではありません。
データ作成者の製作ミスなどにより、本来の機能・性能を出していないこともあります。
本表記載内容は、キット・部品購入時点における情報です。製造中止になったものや変更となっているものもあります。
追加購入部品欄にはケース・配線材料など共通的な部品については記載していません。
改造は各自の責任で行って下さい。
End of This Page.